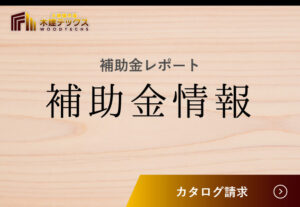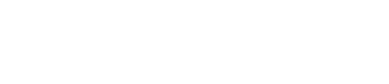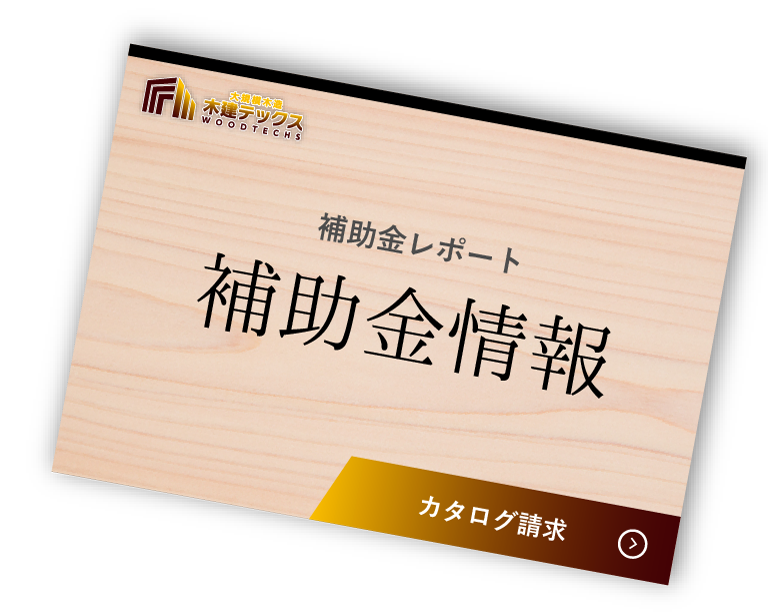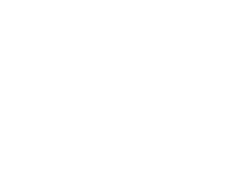みなさんこんにちは。神奈川県にある大規模木造建築専門店の木建テックスです。
「新しく事務所を建設したいけれど、一体いくら費用がかかるのか見当もつかない」「建設費用の坪単価という言葉は聞くけれど、どう計算すればいいのか分からない」など、事務所の建設費用に関して、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。
事務所の建設は大きな投資だからこそ、費用に関する正確な知識は欠かせません。この記事では、事務所の建設費用について、構造別の坪単価の相場から、総額を左右する費用の内訳、そしてコストを賢く抑えるための具体的な方法まで、専門家の視点から徹底的に解説していきます。
この記事を最後までお読みいただくことで、事務所建設にかかる費用の全体像が明確になり、ご自身の予算に合わせた具体的な計画を立てるための第一歩を踏み出すことができます。事務所の新設や建て替えを検討されている経営者やご担当者の方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
事務所の建設費用、坪単価の最新相場は?【2025年版】
事務所の建設費用を考える上で、まず押さえておきたいのが「坪単価」です。坪単価とは、建物の床面積1坪(約3.3㎡)あたりの建築費用のことを指します。ただし、この坪単価は建物の構造によって大きく変動するため、注意が必要です。
構造別に見る事務所建設の費用(坪単価)
事務所の建築で主に採用される構造には、木造、鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)があります。それぞれの構造ごとの坪単価の相場は以下の通りです。
(参考:国土交通省「建築着工統計調査(2023年)」より算出)
表からも分かるように、木造は他の構造に比べて坪単価を大幅に抑えられる傾向にあります。かつて事務所やビルといえば鉄骨造やRC造が主流でしたが、近年の建築技術の進化により、木造でも高い強度とデザイン性を両立した事務所の建設が可能になりました。私たち木建テックスのような大規模木造建築を専門とする会社も増えており、コストを抑えつつ質の高い事務所を建てたい企業にとって、木造は非常に魅力的な選択肢となっています。
【注意】事務所の建設費用は坪単価だけでは決まらない
坪単価はあくまで概算を把握するための目安であり、「坪単価 × 延床面積」だけで正確な総工費が決まるわけではありません。事務所の建設費用は、大きく分けて「本体工事費」「別途工事費」「諸経費」の3つで構成されており、一般的に坪単価で示されるのは「本体工事費」のみであることがほとんどです。
そのため、総額を把握するためには、これらの費用項目をすべて考慮に入れる必要があります。次の章で、それぞれの費用の内訳について詳しく見ていきましょう。
事務所の建設費用の内訳を3つの項目で解説
事務所の建設にかかる総費用は、建物本体の工事費以外にも様々な費用が含まれます。ここでは、総工費の内訳である「本体工事費」「別途工事費」「諸経費」の3つの項目について、それぞれどのような費用が含まれるのかを具体的に解説します。
①本体工事費
本体工事費は、建物そのものを建てるための費用で、総工費の約70%~80%を占める最も大きな部分です。これには、以下のような工事が含まれます。
- 仮設工事: 工事用の足場や仮設トイレ、現場事務所の設置など。
- 基礎工事: 建物を支える基礎を造る工事。
- 躯体工事: 柱や梁、壁、床など、建物の骨格を造る工事。
- 内外装工事: 外壁、屋根、内壁、天井、床などの仕上げ工事。
- 建具工事: 窓やドアなどの設置工事。
- 設備工事: 電気、ガス、水道、空調などの配線・配管工事。
一般的に「坪単価」として提示される金額は、この本体工事費を指している場合が多いことを覚えておきましょう。
②別途工事費
別途工事費は、建物本体以外にかかる工事費用で、総工費の約15%~20%を占めます。土地の状態や周辺環境によって必要な工事が異なり、費用が大きく変動する部分でもあります。
- 解体工事費: 既存の建物がある場合に解体・撤去するための費用。
- 地盤改良工事費: 土地の地盤が軟弱な場合に、建物を安全に支えるために地盤を補強する工事費用。
- 外構工事費: 駐車場、門、塀、アプローチ、植栽など、建物周りの工事費用。
- インフラ引込工事費: 水道管やガス管、電気を敷地内に引き込むための工事費用。
- インテリア・家具購入費: カーテンやブラインド、デスク、椅子などの購入費用。
これらの費用は最初の見積もりに含まれていないケースも多いため、必ず事前に確認することが重要です。
③諸経費
諸経費は、工事以外で必要となる費用で、総工費の約5%~10%が目安です。
- 設計料: 建物の設計を建築士に依頼するための費用。
- 各種申請費用: 建築確認申請など、行政手続きに必要な費用。
- 登記費用: 建物の所有権保存登記や抵当権設定登記などにかかる費用(司法書士への報酬含む)。
- 税金: 不動産取得税、固定資産税、登録免許税、印紙税など。
- 保険料: 火災保険や地震保険などの保険料。
- ローン手数料: 建設資金を金融機関から借り入れる場合の手数料や保証料。
このように、事務所の建設には多岐にわたる費用が発生します。全体像を把握し、余裕を持った資金計画を立てることが成功の鍵となります。
事務所の建設費用を抑える5つの具体的な方法
事務所の建設は大きな投資ですが、ポイントを押さえることで費用を賢く抑えることが可能です。ここでは、すぐに実践できる具体的なコスト削減方法を5つご紹介します。
【コスト削減①】木造を選択して建築費用を抑える
最も効果的なコスト削減方法の一つが、建物の構造に「木造」を選択することです。先ほどの坪単価の比較でも明らかなように、木造は鉄骨造やRC造に比べて材料費や人件費を安く抑えることができます。
特に、建物自体の重量が軽いため、大規模な基礎工事や地盤改良工事が不要になるケースが多く、これが大幅なコストダウンに繋がります。以前、私たちが手掛けた案件で、当初は鉄骨造で計画を進めていた企業様が、予算の都合で木造に変更したところ、総工費を約15%も削減できたという事例もあります。耐震性や耐火性も現在の技術では十分に確保できるため、木造はコストパフォーマンスに非常に優れた選択肢と言えるでしょう。
【コスト削減②】シンプルな形状・デザインにする
建物の形状は、建設費用に大きく影響します。凹凸の多い複雑なデザインや、特殊な形状の屋根は、材料に無駄が出やすく、施工の手間も増えるためコストアップの要因となります。
費用を抑えるためには、できるだけ正方形や長方形といったシンプルな「総二階建て」のような形状にするのが効果的です。シンプルな形状は、耐震性の面でも有利に働くことが多く、デザイン性とコスト、安全性のバランスを取りやすいというメリットもあります。外観や内装も、過度な装飾を避け、シンプルで機能的なデザインを心がけることで、費用を大きく削減できます。
【コスト削減③】適切な業者選びと相見積もり
建設業者によって、得意な工法や使用する資材、そして見積金額は大きく異なります。信頼できる業者を慎重に選ぶことが、結果的にコスト削減に繋がります。
まず重要なのは、複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」です。最低でも2~3社から見積もりを取り、項目ごとに内容を詳細に比較検討しましょう。単に総額が安いというだけで判断するのではなく、工事内容や使用する資材のグレード、アフターサポートの有無などを総合的に評価することが大切です。特に、事務所建築の実績が豊富な業者や、私たち木建テックスのように特定の工法(大規模木造建築など)を専門とする業者に相談すると、より的確なアドバイスやコストを抑えた提案が期待できます。
【コスト削減④】設備のグレードを見直す
事務所に必要な空調設備や照明、トイレ、給湯室などの設備は、グレードによって価格が大きく異なります。最新の高性能な設備は魅力的ですが、本当に必要な機能なのかを一度立ち止まって考えることが重要です。
例えば、全ての照明をハイスペックなものにするのではなく、来客スペースなど限定した場所にデザイン性の高いものを採用し、執務スペースは機能性重視の標準的なものにする、といったメリハリをつけることでコストを調整できます。また、将来的な増設や変更が容易な設計にしておくことで、初期投資を抑えるという考え方もあります。自社の事業内容や働き方に合わせて、設備の優先順位を決めていきましょう。
【コスト削減⑤】補助金や助成金を活用する
国や地方自治体は、省エネルギー性能の高い建物の建築や、国産木材の利用促進のために、様々な補助金や助成金制度を用意しています。これらの制度をうまく活用することで、建設費用の一部を補うことが可能です。
例えば、木造で事務所を建てる場合、林野庁や各地方自治体が実施している、建築物における木材の利用を促進するための様々な補助金や助成金制度が活用できる可能性があります。どのような制度が利用できるか分からない場合は、建設を依頼する業者に相談してみるのも良いでしょう。補助金活用に詳しい業者であれば、申請のサポートも期待できます。
参考)林野庁、木材の利用の促進について
事務所建設で後悔しないための注意点
コストを抑えることばかりに目を向けていると、完成後に「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、費用面以外で事務所建設を進める際に注意すべきポイントを解説します。
ランニングコストも考慮した資金計画を立てる
事務所の費用は、建てて終わりではありません。完成後には、固定資産税や都市計画税といった税金、火災保険料、そして定期的なメンテナンス費用など、様々なランニングコストが発生します。
特に、光熱費は毎月発生する大きなコストです。初期費用が多少高くなったとしても、断熱性能の高い建材を使用したり、省エネ性能の高い空調設備やLED照明を導入したりすることで、長期的に見れば光熱費を大幅に削減でき、トータルコストを抑えることができます。建設時の初期費用(イニシャルコスト)だけでなく、将来にわたってかかる費用(ランニングコスト)も考慮に入れた、長期的な視点での資金計画が非常に重要です。
デザイン性と機能性のバランス
企業の顔となる事務所の外観や、社員が気持ちよく働ける内装デザインは、企業のブランディングや人材確保の観点からも重要です。しかし、デザイン性を追求するあまり、業務に必要な機能性が損なわれては本末転倒です。
例えば、「デザインは素晴らしいけれど、コンセントの数が足りない」「開放的でおしゃれだが、声が響きすぎて集中できない」といった問題が起こりがちです。設計段階で、社員の動線や働き方を十分にシミュレーションし、デザイン性と機能性の両方を満たすプランを練ることが大切です。収納スペースの確保や、将来的な人員増加に対応できる柔軟なレイアウトなども、忘れずに検討しておきましょう。
まとめ
事務所の建設費用は、坪単価を基準に考えますが、実際には建物の構造、規模、立地、設備のグレードなど、様々な要因によって大きく変動します。費用を正確に把握するためには、総工費が「本体工事費」「別途工事費」「諸経費」の3つで構成されていることを理解し、それぞれの内訳をしっかりと確認することが重要です。
建設費用を抑えるためには、シンプルな設計を心がけたり、補助金を活用したりする方法がありますが、最も効果的な方法の一つが木造を選択することです。木造建築は、坪単価が他の構造に比べて安く、工期も短縮できるなど多くのメリットがあります。
事務所の建設は、企業にとっての一大プロジェクトです。この記事で紹介した費用に関する知識を参考に、信頼できるパートナー(建設会社)を見つけ、後悔のない事務所建設を実現してください。
木建テックスでは、大規模木造建築の専門家として、お客様のご予算やご要望に応じた最適な事務所建設計画をご提案いたします。費用に関するご相談や概算見積もりも無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。(TEL:0465-20-3381)